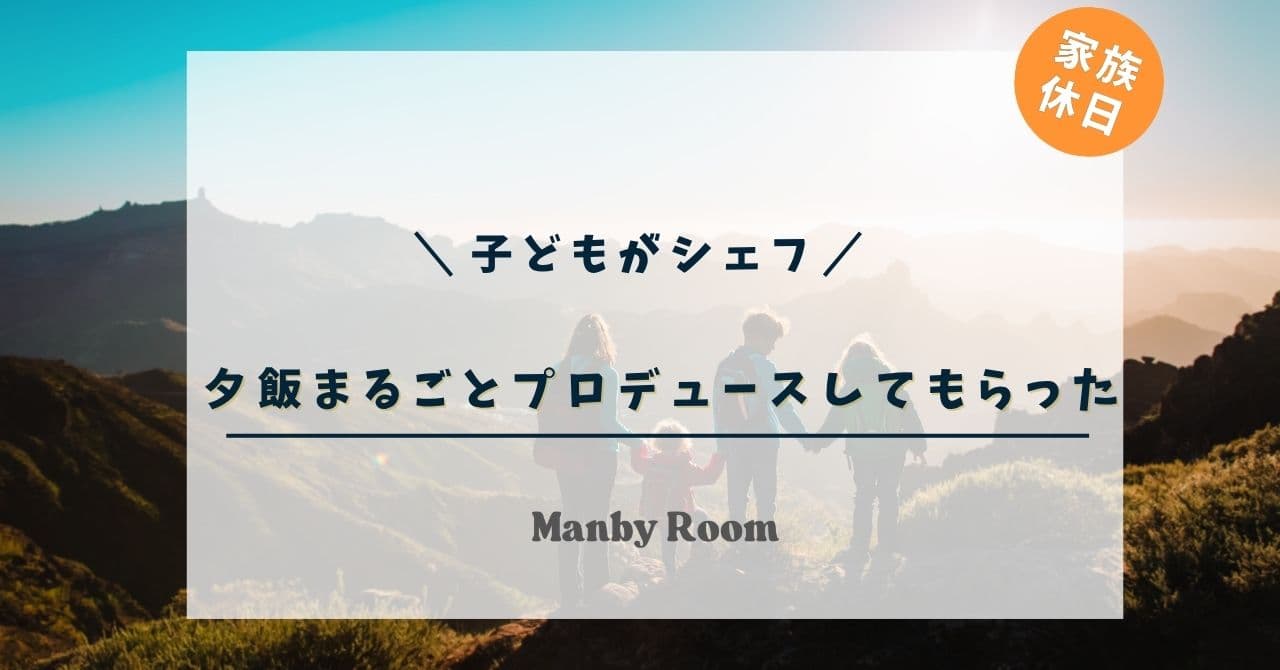「今日は○○が晩ごはん、考えてみる?」
そんな一言から始まった“子どもプロデュースの夕飯”企画。
この日は、献立づくりから買い物、調理、盛り付けまで、できる範囲で子どもにすべて任せてみることにしました。
この記事では、
「子どもに夕飯づくりをまかせてみる」という体験が、
どんな時間になったのか
実際にやってみて良かったこと・大変だったこと・工夫した点などを、リアルなエピソードを交えて紹介しています。
「いつもの食事を、ちょっと特別にしてみたい」
そんな方のヒントになれば嬉しいです。
子どもに夕飯を任せてみようと思った理由とその日の流れ

きっかけは、本当にちょっとした一言でした。
その日は週末で、夕方から家族でスーパーに行く予定だったんですが、買い物の直前に「今日の晩ごはん、○○が考えてみる?」と何気なく声をかけてみたんです。
すると子どもは「えっ、いいの?やってみたい!」と、思った以上にノリノリ。
そこから、“子どもがシェフになる日”がスタートしました。
買い物に向かう車の中では、
「何作る?」「何が食べたい?」「予算は?」と作戦会議。
食べたいものをベースに、サラダもつけよう、お皿はこうしよう、など話が広がっていく様子に、こちらもワクワクしちゃいました。
この日の流れはざっくりこんな感じ:
✓ 子どもと一緒に献立を決める(好きな料理+1品野菜ルール)
✓ スーパーで食材を選ぶ(メモを書きながら自分でかごへ)
✓ 調理スタート(包丁はサポート、でも炒めは担当)
✓ 盛り付けとテーブルセット(お箸やコップも並べてもらう)
✓ 「いただきます」まで子ども主導で進行!
選んだメニューは「カレーライスとカラフルサラダ」
具材はすべて子どもが決め、「ニンジンは星型にしよ!」「赤と黄色のパプリカも入れたい」など、アイデア満載。
サラダにはドレッシングを3種類並べて「選べる方式」にするなど、まるでレストランのような演出までしてくれて。
いつもならバタバタと終わる夕方の時間が、この日はじっくり親子で会話しながら進められて、普段とは違う充実感がありました。
やってみて実感!良かったところ

正直、最初は「本当にできるかな?途中で飽きちゃうかも…」と不安もありました。
でも、いざスタートしてみると、予想以上に前向きに、しかも工夫しながら取り組む姿にこちらが驚かされる場面がたくさんありました。
やってみて特に「これはよかった!」と感じたポイントはこちらです:
✓ 段取りを自分なりに考えるようになった
カレーを作る時、「じゃがいもは先に切る?それともにんじん?」と、自分の頭で順序を組み立てている様子がありました。
「わからないけど考えてみる」という姿勢自体が、大きな成長だなと思いました。
✓ 野菜への興味が湧いた
普段はサラダに入っていてもスルーするようなパプリカや紫キャベツも、「色がきれいだから入れてみたい!」と自分からチョイス。
食べるときには「この野菜、自分が選んだやつだよ」とちょっと得意げで、苦手な食材との距離が少し縮まったような気がします。
✓ “自分の料理”という意識が高まり、ごはん時間が特別に
盛り付けや食卓の準備までこだわってくれて、「○○レストランへようこそ!」なんて看板まで書いていました(笑)
食べている間も、「カレーの味、どう?」「おかわりする?」と小さな店主のようにふるまってくれて、家族みんながあたたかい気持ちに。
ただの“ごはんを作る”体験ではなく、“誰かのために用意する”という意識が芽生えていたのがとても印象的で、ほっこり。
子どもって、思っている以上にいろんなことを考えてるんだな、と改めて感じる機会になって、
ちょっとした「任せてみる」だけで、こんなにも伸びしろがあるんだな…と、親のほうが学ばされる場面ばかりでした。
思ったより大変だったことも…正直な感想

やってよかった、と思う一方で…やっぱり「大変だった!」というのも正直な感想です。
特に初めてだったこともあり、こちらが想像していなかった“ハプニング”や“時間のロス”も多々ありました。
✓ とにかく進行がゆっくり!予定より1.5倍かかる
野菜を切るだけでも時間がかかるし、「どっちの包丁がいいかな…」「皮むきって、どうやるんだっけ?」と一つ一つ立ち止まりながら進むので、夕飯の支度に想像以上の時間がかかりました。
しかも、「星型にんじんを作る!」と型抜きに夢中になって、なかなか本題の調理に入らない場面も(笑)
✓ 途中で集中が切れがち
最初は張り切っていたのに、10分後には「疲れた〜」と言って床にゴロン。
「あとちょっとだけ頑張ろう!」と励ましたり、作業を交代したりして、テンションを切らさず進めるのに工夫が必要でした。
「自分で決めたことをやり抜く」ことの大切さを感じてもらうためにも、最後まで寄り添うこちらの忍耐力も問われる時間だったなと思います。
✓ こちらの“想定外”が次々に起こる
「カレールーはこの大きいの全部入れちゃっていい?」とか、「味見してみるね」とお玉1杯分を試食しようとしたりとか…。
「おっと、それはちょっと待って!」というシーンが何度かあり、内心ドキドキでした(笑)
それでも、頭ごなしに止めるのではなく、「どうしてそう思ったの?」と聞くように意識すると、本人なりの理由がちゃんとあることが分かってきます。
この日、私自身が一番学んだのは、「任せる」って“放任”ではなく、“見守る勇気”がいるんだなということ。
時間が押して焦る気持ちや、「自分でやったほうが早い」という思いをいったん脇に置いて、子どもの選択や行動を信じてみる――
この“親の踏ん張りどころ”が一番大変だったかもしれません。
スムーズに進めるために工夫したこと

1回目は正直バタバタでしたが、そのぶん「次はこうしてみよう」と気づいたこともたくさんありました。
任せるとはいえ、“全部を丸投げ”ではなく、ちょっとした準備と声かけでぐっとスムーズになることが分かってきました。
✓ メニューは事前に2~3案用意して、選択式に
「好きなもの作っていいよ」と言うと、悩みすぎて進まなかったり、突拍子もないリクエストが出たりします(笑)
そこで、「今日はカレーにする?それともチャーハン?」のように、選択肢をしぼって“自分で決めた感”を残す工夫をしました。
✓ 買い物リストを一緒に作ると買い物がスムーズに
食材選びで迷いすぎて時間がかかることもあったので、あらかじめリストを一緒に作成。
「人参いくつ必要?」「ドレッシングはどれがいい?」と、具体的に考える機会にもなりました。
メモ帳を持たせると、ちょっと大人になった気分で楽しんでくれるようです。
✓ できたところでたくさん褒める&効果音も◎
たとえ少ししか切れてなくても「おぉ〜すごいね!切れてる切れてる!」とオーバーにリアクション。
「よしっ!○○シェフ、次はお皿に盛り付けお願いしますっ」など、演技入りで乗せていくと本人のやる気もUP。
効果音をつけたり、BGMを流すだけでも雰囲気が変わって大盛り上がり。
✓ “安全ゾーン”を決めて任せすぎない
包丁や火を使う工程は、無理せず一緒に作業。
「ここからは交代しようか」「これはお手伝いするね」と声かけをしながら、あくまでも“楽しい”をベースに進めました。
こうしたちょっとした準備やテンポ作りのおかげで、2回目・3回目になるほどお互いのペースもつかめてきて、「またやってみようか」が自然に生まれるように。
「楽しかった」「またやりたい!」を引き出せれば大成功!
そのために、大人側が“ちょっとだけ仕掛ける”のがコツかなと思いますよ。
まとめ|“まかせる夕飯”は親子のいい時間になる

子どもに夕飯づくりをまかせるのは、想像以上に体力と時間がいるチャレンジでした。
でも、それ以上に感じたのは、その過程にあるたくさんの「学び」と「つながり」です。
段取りを考える力、相手のことを思う気持ち、やりきった達成感。
何より、普段は見えなかった子どもの表情やこだわりに触れられたことが、いちばんの宝物になりました。
そして、ただ料理をするだけじゃなく、
-
「自分で選ぶ」「考える」「やってみる」
-
「失敗しても、まあいいかと思える雰囲気」
-
「親も子も、ちょっとだけ役割を変えてみる」
そんな時間を共有できたことが、家族にとっての特別な思い出になった気がします。
毎日やるのは難しくても、月に1回でも、季節の節目でもいい。
「今日は○○がシェフの日!」と決めるだけで、親子のコミュニケーションに新しい風が吹くかもしれません。